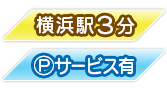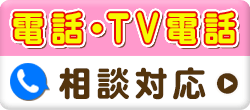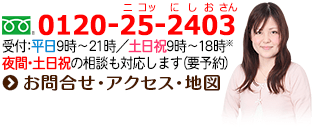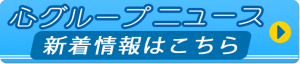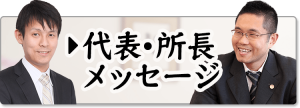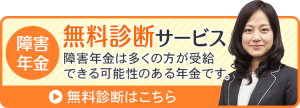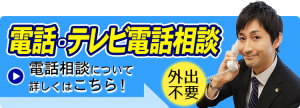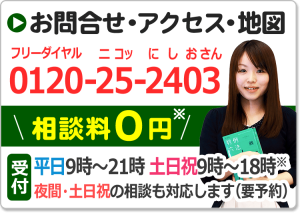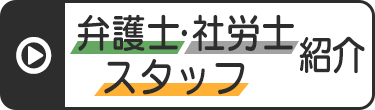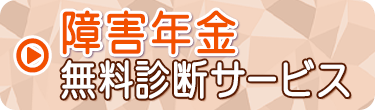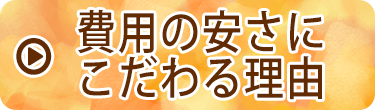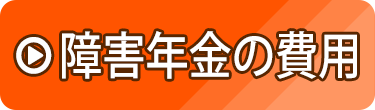HIV感染症で障害年金を請求する場合のポイント
1 HIV感染症での障害年金申請について
HIV感染症も、受給の要件を満たしていれば障害年金の受給が認められます。
以下では、申請についての要件やポイント等についてご説明していきます。
2 初診日について
障害年金の申請においては、初診日(申請傷病について初めて医療機関を受診した日)が重要になってきます。
「申請傷病について初めて」ですので、HIV感染症と診断された日(確定診断といいます。)とはならない可能性があります。
特に、HIV感染症の初期症状は風邪やインフルエンザに似た症状が出るとされ、かつ数日程度で症状も消えてしまうとされていることから、過去に風邪だと思って通った内科等を受診した日が初診日であるということがあります。
また、潜伏期間が長く、感染の事実が何年も後になって発覚することもあり得ます。
その場合、カルテ等の医療記録が残っているかという問題が生じることもあります。
HIV感染症のこういった特殊性から、感染に至った経過等をできるだけ明確にしていき、初診日の通院先となる医療機関を明らかにすることがポイントとなってきます。
3 保険料納付について
保険料納付要件については、HIV感染症か他の申請傷病かで大きな違いはありません。
基準としては、初診日の属する月の前々月まで(例えば4月10日が初診日の場合は2月分まで)の納付状況について、①直近1年間で保険料の未納がないか、②納付開始から現在まで1/3を超える未納がないかのどちらかを満たす必要があります。
免除手続きを経た上で納付していない分は未納とは扱われませんが、上記の要件を判断するのは初診日の前日時点で、となっているため、後日免除手続きをとったからといって納付要件が事後的にクリアされるわけではありませんのでご注意ください。
4 障害状態について
HIV感染症の障害状態の認定基準は、大枠として、検査項目の数値についての基準、症状についての基準、HIV感染症の既往歴の有無等という3つの観点から総合的に定められています。
検査項目は、例えばCD4値について3級では350/μl以下、1級及び2級では200/μl以下とされています。
その他、白血球数、ヘモグロビン量等の項目があります。
身体症状については、例えば月に7日以上の不定の発熱、1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上、生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限等があります。
数値が一定以下、身体症状が一定数以上発現している等といった状態から、最終的な等級が定められます。
数値は検査次第ですが、身体症状については、しっかり医療機関に伝えていないと、医師も実際の症状を捉えた診断書の作成ができなくなってしまいますので、通院中にしっかり医師に病状を伝えることが大切になってきます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- ダウン症で障害年金を申請する際のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- HIV感染症で障害年金を請求する場合のポイント
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止となるケース
- 過去に遡って障害年金の支給停止解除を行った事例
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒221-0056神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
0120-25-2403